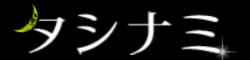日本語を母国語として使っている私たち。
海外の人から見ると、日本語は、中国語やアラビア語と並んで最も難しい言語枠に入っていると言われています。私たち日本人でも、日本語を完璧に操っている!と自信をもって言える人の方が少ないのではないでしょうか?
日本語が難しい理由として、
・ひらがな・カタカナ・漢字の使い分け
・漢字の音読みと訓読み
・直接的ではなくて婉曲的な表現が多い
・助詞(は・が・に・で・を)の使い方で文章の意味が変わる
・のばしたり、1文字では読まない音(っ・ゃ・ゅ・ょ)が入ったりする
・ものによって数え方が変わる
ざっと調べるだけでも、これだけのことがでてきました。
そして日本人には、相手を気遣い、礼儀を重んじる精神文化が少なからずあります。それに必要なのが日本特有の『敬語』であって、こちらも日本語の難しい理由のひとつだと言われています。

いくら仕事ができても、言葉づかいがよくないと信用を失うことがあるかもしれません。
丁寧な言葉づかいを心がけていても、その意味を誤って使っていては、違和感を与えてしまったり、伝えたいことが伝わらなかったりするかもしれません。だからといって、言葉を意識しすぎた結果、おかしな敬語になってしまうこともあります。
そこで今回は、敬語の使い方や、実は間違っている敬語の使用例などをご紹介していきたいと思います。
話す相手が、お客様や取引先、初対面の方、自分より目上の方や年上の方といった場面でも、適切な敬語を使っていくことによって、ワンランク上の大人を目指していきましょう!
尊敬語と謙譲語

敬語は、丁寧語・尊敬語・謙譲語に分けられます。
丁寧語:言葉を整えて丁寧に表現する言葉
尊敬語:相手の立場を高めることで敬意を示す言葉
謙譲語:自分をへりくだることで相手に敬意を示す言葉
これが頭ではわかっているけど、なかなかはっきりと使い分けができないのが敬語の難しさですよね。ですので、以下に混同しがちな尊敬語と謙譲語の例をご紹介します。
〇〇様でございますね。
『ございます』は物や状況が『ある』という言葉の丁寧語で、人に対しては使いません。人の存在に対して敬意を示したい場合は『いる』の尊敬語の『いらっしゃる』を使います。
【正解】〇〇様でいらっしゃいますね。
どちらにいたしますか?
『いたす』は『する』の謙譲語ですが、この動作は自分ではなく、敬意の対象である相手です。ですから、動作をする相手に対して『いたす』と謙譲語を使うと相手の立場を低くしてしまうため、『する』の尊敬語である『なさる』を使います。
【正解】どちらになさいますか?
お名前を頂戴してよろしいでしょうか?
『頂戴する』は『もらう』の謙譲語です。
『もらう』という言葉は物に対して使うので、「名刺を頂戴してよろしいでしょうか?」という使い方ならOK。名前はあげたりもらったりするものではないし、名前を聞きたいわけなので、『聞く』の謙譲語である『伺う』や『お聞きする』といった表現にします。
【正解】お名前をお伺いしても(お聞きしても)よろしいでしょうか?
ご拝読いただきありがとうございます。
この場合、読んだのは相手であり、『拝読』は『読む』の謙譲語ですので、自分がへりくだるのではなく相手に対しての尊敬語にするべきです。『読む』を尊敬語である『ご覧になる』『お読みになる』とすることが正しい使い方です。
【正解】ご覧いただき(お読みいただき)ありがとうございます。
上司にも申し上げておきます。
この場合は少しややこしいのですが、文章の中に、自分と上司と話している相手の三者が存在します。
相手が取引先であった場合は、社内の人間である上司の立場を高めることはしません。ですから、『申し上げる』という表現をすると、上司に対してへりくだる謙譲語を使っていることになります。
これを『お伝えする』という尊敬語に言い換えた場合、対象は伝える先の上司になるため、こちらも取引先の前で上司をたててしまいます。
これを、『申し伝える』とすると、『言い伝える』の謙譲語なので、伝える先の上司ではなく、聞いている相手である取引先をたてることになります。そうすれば、上司もいっしょにへりくだり、相手に敬意を示す表現に変わります。
【正解】上司にも申し伝えておきます。
二重敬語

二重敬語とは、尊敬語を重ねたり、謙譲語を重ねたり、尊敬語と謙譲語を合わせて使ってしまうことです。
目上の人や取引先に過剰に敬語を使おうと、敬語を二重にも三重にもしたとしても、丁寧さや敬意のレベルは上がりません。むしろ違和感を与えてしまうこともあるので注意しましょう。
資料はご覧になられましたか?
『見る』を尊敬語にする場合、『ご覧になる』、または「れる・られる」をつけて『見られる』となります。この場合は、尊敬語に変化させたものを、さらに尊敬語を付け加えて変化させた間違った表現です。
【正解】資料はご覧になりましたか?
〇時にお伺いいたします。
一見問題はなさそうですが、こちらも誤りなんです。『訪問する』の謙譲語である『伺う』に、『お~する』が重なって『お伺いする』になり、さらに『する』の謙譲語の『いたす』も重なって用いられている例です。
【正解】〇時に伺います。
お客様が参られました。
こちらは謙譲語と尊敬語を合わせて使ってしまっている例です。
『来る』の謙譲語である『参る』に、「れる・られる」の尊敬語が誤って組み合わされています。この場合は『来る』の尊敬語である『お見えになる』『お越しになる』、『いらっしゃる』を使います。
【正解】お客様がお見えになりました。
二重敬語にならないようにするためには、とにかくシンプルな表現をするように意識するようにしましょう。
よく間違えられている敬語

それでは以下に、よく使われているけども実は間違っている敬語をご紹介します。
ご注文は〇〇でよろしかったでしょうか?
こちらは、相手に配慮をし、自分の行動が正しいかどうか再確認する際の言葉を丁寧に言おうとしたものです。
『よい』を丁寧に言い換えると『よろしい』、これを過去形にすると『よろしかった』です。前提となる過去の内容があり、それに対しての確認の意味で用いるなら『よろしかった』は適切と言えます。
ですが、確認しているのは今起こっていることで過去のことではないのにも関わらず、過去形の表現にしてしまっています。よって、今現在の物事への確認の場合は、現在形で「よろしいでしょうか」と言いましょう。
【正解】ご注文は〇〇でよろしいでしょうか?
私のほうで担当いたします。
ここで気になるのが「~のほう」なんですが、これが口癖のようになっている人がいます。
「こちらのほうにサインのほうお願いします」
「〇〇のほうは出張のほうに出ております」などなど。
「~のほう」は比較対象がある場合に用いられるものです。そのため選択肢がある中で「このほうがいい」という使い方ならOK。また「あちらのほうへ」と方角を示す使い方も問題ありません。
ですが、比較する物がなく1つの物を示すときに使うのは誤りです。
【正解】私が担当いたします。
こちらが資料になります。
「なる」という動詞は、別の何かに変化することを表します。したがって、変化しないものに対して、「なる」を使用するのは誤りです。
【正解】こちらが資料でございます。
1000円からお預かりします。
コンビニなどでよく聞くこのフレーズ。
『お預かりします』という敬語は間違っていないのですが、「から」の使い方に問題があります。「から」を使う場合は、対象となる「誰か」から物を受け取るときなので、「から」の前が人ならOK。
この使い方だと、敬語の対象となる人からではなく、1000円から預かっていることになってしまいます。
【正解】1000円お預かりします。
250円ちょうどお預かりします。
次は、会計金額が250円の場合に、ぴったりの金額を受け取るときのケース。
物を預かるとお返しする必要がありますが、金額がちょうどの場合、返すお釣りはありませんよね。したがって、『お預かりします』という言い方が誤りです。
【正解】250円ちょうどいただきます。
使い方に注意したい敬語

とんでもございません。
これは使い方が間違っているのに、それが一般的になってしまっている敬語の代表例です。
褒められたり、お礼を言われたりしたときに、謙遜の意味をこめて使われていることが多いですが、「とんでもない」という言葉は、「ぎこちない」「くだらない」などと同じ形容詞であって、「~ない」まで含めてひとつの単語なんです。
「ぎこちない」を『とんでもございません』と同じような使い方をすると『ぎこちございません』になってしまいます。
こんな使い方はしませんよね?
ひとつの単語なので「ない」の部分だけを「ございません」に変換することはできないわけです。「とんでもない」は「うれしい」「おもしろい」と同じように使うと覚えておきましょう。
【正解】
とんでもないことでございます。
とんでもないです。
とんでもないことです。
恐れ入ります。
こちらは使い方によって、違った意味をもつ言葉です。
もともとは相手に対して、「自分は到底あなたには敵いません」という敬意が含まれています。
言葉の初めに「恐れ入りますが」と添えることで、相手に頼みごとをしたり、何かを尋ねたりするとき、話しやすい雰囲気を作ることができます。相手に面倒をかけることに対し、申し訳ないというへりくだった気持ちを表現するものです。
例:恐れ入りますが、〇〇様はいらっしゃいますか?
そして、自分にとっていい評価をしてもらったときや、何かをしてもらったときに使うと、謙遜と感謝の気持ちの両方を表すことができます。
例:わざわざご連絡いただき、恐れ入ります。
ただ『恐れ入る』に申し訳ないという意味があるからといって、自分に非がある場合に使うと、おかしなことになってしまいます。
伝わりにくい説明で恐れ入ります。
文末に『恐れ入ります』を使うときは要注意です。
この使い方ですと、感謝の意味を含むこともあるため、伝わりにくい説明で恐縮だけどありがとう!という意味に捉えられる可能性もあります。
【正解】伝わりにくい説明で申し訳ございません。
恐れ入りますが、ご希望に添いかねる結果となりました。
こちらは、都合により相手に迷惑をかける結果になってしまっていることから、きちんとお詫びの気持ちを表すことが必要です。
『恐れ入りますが』は、とりたてて謝る必要がないけども、こちらから何かをお願いするときに、相手を不快にさせずに聞いてもらうために使うクッション言葉です。この場合は謝罪の意味をこめて『申し訳ございませんが』という言葉を使いましょう
【正解】申し訳ございませんが、ご希望に添いかねる結果となりました。
最後に
ここで紹介できていない誤った敬語の使い方の例は、まだまだ存在します。それほど日本語というものは奥が深く、難しいものなんですね。
今回は、代表的な間違えやすい例と【正解】を書きましたが、その回答だけが正しいというわけではありません。敬語を使う場面で、それが正しいのか心配になったのなら、日本語だからこそ別の表現に言い換えることもできてしまうんです。
敬語は、コミュニケーションのための大切なツールです。
ですが、敬語を使おうと意識しすぎた結果、敬意の対象が不明瞭になって、かえって失礼にあたることもあります。そこで最低限のルールを知っておけば、相手の立場を尊重する気持ちを表せるし、意思をはっきりと伝えることができます。
言葉づかいが変わると、自分に対する印象や信頼もよいものに変わってくるでしょう。そんな大人としてビジネスとしての基本のマナーである正しい敬語を、きちんと身につけておきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。